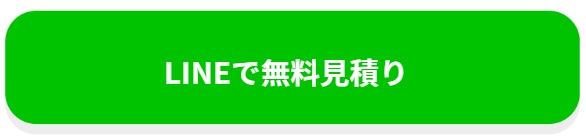引っ越し荷造りのコツや順番を徹底解説!間に合わない時はプロに依頼も【引越しノウハウ】

整理収納サービス『おうちデトックス』代表 大橋わか
お宅訪問件数450案件・1,500回以上。実生活でキレイを維持できる整理収納を教える片付けコンサルティングサービスおうちデトックスの代表
「引っ越しの荷造りって、どこから始めればいいの?」と悩む方は多いのではないでしょうか。
引っ越し準備は、やるべきことが多くて混乱しやすいもの。段取りを決めずに荷造りを始めると、必要なものがすぐに見つからなかったり運搬中に荷物が壊れたりするなど、トラブルにつながりかねません。
この記事では、引っ越し荷造りをスムーズに進めるために準備するものやスケジュール、そして荷物ごとのコツや荷造りのポイントについて、詳しく解説します。
忙しくて自分で作業するのが難しい場合は、収納のプロに依頼する方法も。詳しくはこちらをご覧ください。
目次
引っ越しの荷造りで必要なアイテムは?
まず、引っ越しの荷造りで必要なアイテムを紹介します。これらのグッズを事前にそろえておけば、荷造り作業がスムーズに進みますよ。
ガムテープ・養生テープ
ガムテープや養生テープは、段ボールをしっかり閉じるために使います。また、不安定な荷物や使いかけのボトルキャップなどを固定する時にも、役立つアイテムです。
ガムテープは粘着力が高い一方で、剥がす際に残りやすい粘着跡がデメリット。もう1つの養生テープは粘着力がほどよく、家具や床を傷つけずに固定できます。テープの強度によって、使う場所を考えるようにしましょう。
なお、荷物を区別するために色分けされたテープを使うと、新居での荷解きがより効率的です。
ビニール紐
ビニール紐は、軽い荷物やまとめたいものを束ねる際に使います。
特に、雑誌や本をまとめる際に活躍しますが、それ以外でも、掃除用具や物干し竿といった長いものは、一括して縛って固定すれば運搬中のトラブルを防げます。また、ビニール紐を使う際は、結び目を簡単に解けるよう工夫すると、荷解きの時間短縮につながりますよ。
紐にもいろいろな種類がありますが、やはり丈夫なビニール紐がおすすめです。
軍手
軍手は、手を保護するために使用するアイテムです。
引っ越し作業中は、家具や重い荷物を持つことが多く、手をケガしてしまう場合があります。段ボールや書類で手を切ってしまうこともあり、軍手があると安心です。
軍手は滑り止め付きタイプを使えば、物をしっかり掴めるだけでなく、力が入りやすくなって安全性もアップ。特に大型家具や重い段ボールを運ぶ際には、必須のアイテムです。
作業中に汚れても気にならないよう、数セット準備しておきましょう。
油性マーカー
油性マーカーは、段ボールの中身を把握するための必需品です。
中に何が入っているか、どの部屋に運ぶべきかを段ボールの側面と上面に記入しておけば、新居での荷解きがスムーズになります。太字のマーカーを使うと目立つので、おすすめです。
また、色違いのマーカーを用意しておけば、部屋ごとに色分けして管理できます。特に赤色のマーカーは、中身によって「割れ物注意」や「天地無用」といった注釈も目立ちやすく書けますよ。
工具・ハサミ・カッター
工具は、家具の一時的な分解や新居での再組み立てに使います。プラスドライバーと六角レンチがあれば事足りるでしょう。
特に大型家具や収納家具は、そのまま運ぶのが難しく、分解する必要があるものも。分解時に外したネジや部品はビニール袋にまとめておき、中身のラベルを貼っておけば、再組み立て時のトラブルを防げますよ。
また、ハサミやカッターは、荷造り時に使うテープや紐の切断で活躍します。また、荷解き時にもあるとスムーズに開封できて便利です。引っ越し時には常に携帯することになりますが、あせって手を切らないよう、取り扱いには十分に気をつけましょう。
ビニール袋
細かい部品やネジ類をまとめて保管するのに便利なビニール袋は、調味料や洗剤といった液体物を運ぶ時にも活躍するアイテムです。タオルや衣服など、軽いものをまとめるにも使えます。
ビニール袋は、破れにくく丈夫なタイプを選ぶと、破れたり液体が漏れたりせずに安心です。また、濡れたものを一時的に入れておくこともできるので、多めに用意しておきましょう。
なお、引っ越し作業では大量のゴミが発生しますので、大きめのゴミ袋も必要です。
掃除用具
引っ越しの際には、掃除用具も準備しておきましょう。
今まで住んでいた家は、きれいに掃除してから返却しなければなりません。また、新居側も汚れやホコリが残っていることもあり、家具や電化製品を置く前には掃除が必要です。
掃除用具としては、雑巾やウェットティッシュなどが挙げられます。さらにフローリングワイパーやハンディクリーナーもあると、掃除がよりスムーズです。ハンディクリーナーは、事前の充電をお忘れなく。
なお、新居でも使う家電製品や家具にはホコリが溜まっていることも。引っ越しの機会に掃除しておくと、さっぱりとした気分で新居での生活をスタートできますよ。
引っ越しの荷造りで必要な「梱包資材」は?
次に、引っ越しの荷造りで必要な「梱包資材」を紹介します。
段ボール
段ボールは、引っ越しで運ぶものを収納する梱包資材です。4人家族で、おおよそ50箱ほど必要となります。
引っ越し業者に頼む場合、段ボールは無料でもらえる場合もあるため、事前に確認しておきましょう。不足することがないよう、多めにもらうのがポイントです。
使い古しの段ボールは耐久性に難があるため、引っ越しで重たいものを入れる場合は新しい段ボールを使いましょう。組み立ての際は底抜け防止のため、必ず十字にガムテープを貼るようにしてください。
小さめの段ボールは本や小物などの重い荷物向け、大きめの段ボールは衣類や布団など軽い荷物に適しています。入れるものによって使い分けましょう。
なお、段ボールはホームセンターなどでも購入できますが、薄いものは重みで底が抜けてしまうことも。荷物が入れやすいよう、しっかりとした厚みの段ボールを選びましょう。
段ボールを自分で買う場合は「引越し段ボールセット」などと検索すると、段ボールや緩衝材、布団袋などがセット販売されていて便利なものもあります
気泡緩衝材(プチプチ)
壊れやすい荷物を保護するのに役立つのが、プチプチと呼ばれる気泡緩衝材です。
主に食器やガラス製品などを包むことで、輸送中の破損を防げます。また、クッション性があるので、電子機器や家電の梱包や、段ボールの隙間を埋める際にも使用できます。
気泡緩衝材はホームセンターで入手できます。使う量が多い場合は、1,000~2,000円ほどで売られている「ロールタイプ」を購入すると、コストを抑えられますよ。
紙緩衝材(ポーカスペーパー)
紙の緩衝材も、ネットやホームセンターで入手できます。薄い紙ですが、食器を巻いたり段ボールの隙間に入れたりと、丈夫で使い勝手が良いアイテムです。
一枚ずつに分かれているタイプとロールタイプの2種類があります。ロールタイプは手で破って使用。プチプチよりも場所を取らず、お引っ越し後に捨てやすいのがメリットです。
紙製で再生紙が使われていることが多く、地球に優しいのも嬉しいポイントですね。
新聞紙
気泡緩衝材(プチプチ)が手に入らない場合でも、新聞紙で代用可能です。
新聞紙は、ガラスや食器類を包む際にクッション材として使用できます。また、段ボールの空いたスペースに詰めることで荷物が動くのを防げます。
引っ越しで必要となる量は、1~2週間分ほど。新聞紙は安価で入手しやすいので、多めに用意しておくと安心です。
新聞紙が用意できるのであれば、無理にプチプチを購入しなくても大丈夫ですよ。
古いシーツやバスタオル
不要なシーツや毛布は、大型家具や家電を保護するために役立つアイテムです。
大きめの布を家具や家電に巻き付けておくと、輸送中のキズや衝撃から守れて安心です。また、使い古しのものであれば、使い終わった後は処分すればよく、手軽に使えます。
なければ無理して用意する必要はありませんが、引っ越し前の整理で不用品として処分するものがあれば、取っておきましょう。
引っ越しで荷造りする順番とスケジュール
さらに、引っ越しで荷造りする順番とスケジュールについても、詳しく見ていきましょう。
1ヶ月前:家の中をグループ分けする
引っ越しの1ヶ月前より、家の中をグループ分けしていきましょう。グループ分けすることで、新居で荷解きの優先順位が明確になり、スムーズに進められます。
グループ分けは、例えば「リビング」「寝室」「子供部屋」「洗面台」「浴室」といった具合で名前をつけていきます。簡単な間取り図を作っておくと、家族や業者に共有できて便利です。
また、荷造りの際には、できるだけ新居の部屋別に梱包しておくと、後の作業が楽になります。
1ヶ月前:不要なものを処分する
グループ分けが終わったら、新居では不要なものを処分していきましょう。
事前に不要なものを処分すれば、新居での荷解きが楽になり、段ボールなどの資材も節約できます。荷物が減って、引っ越し自体のコストを抑えられるメリットも。
不要なものは捨てるだけでなく、リサイクルショップをはじめ、ネットオークションやフリマアプリなども活用すれば、お得に処分できます。時間がない時は、家の近くのリサイクルショップで処分するのが手っ取り早いでしょう。
不用品を無料で譲り合える掲示板サービスの「ジモティ」なら、自宅や家の近くで取り引きできる上に、梱包も不要ですので、大型の衣装ケースなどを処分したい時におすすめです。
なお、粗大ゴミは引き取りに時間がかかるので、余裕を持って処分しましょう。
2~3週間前:使う頻度が低いものから梱包する
グループ分けや不要物の処分が進んだら、普段あまり使用しないものから梱包を始めましょう。
使わないものを先に箱詰めすることで、荷造りを早く進められる上に、引っ越し当日でも必要なものをすぐに見つけられます。
例えば、季節外れの衣類や書籍、日用品のストックや飾り小物などは、2~3週間前から荷造りしていきましょう。
なお、段ボールには中身を記載し、どの部屋に運ぶかも明記しておくと、新居での荷解きがスムーズです。
3~5日前:家電や家具の準備に取り掛かる
引っ越しの日が近づいてきたら、家電や家具の準備にも取り掛かりましょう。大きなものは分解などが必要で時間がかかるため、当日ではなく早めの準備がおすすめです。
例えば、冷蔵庫に入れるものは計画的に使い切り、電源を抜いて水抜きしておきます。大型の家具は工具で分解して、運びやすくまとめてください。
なお、調理系の家電も、引っ越し前の数日間を加工食品や外食で済ませるようにすれば、早めに梱包できます。
前日~当日:普段使うものをまとめて梱包する
引っ越し当日まで使用する頻度が高いものは、最後に梱包します。「当日セット」を作っておくと、引っ越し後すぐに使いたいアイテムが取り出しやすくなり便利です。
例えば、歯ブラシ、調理器具、着替え、トイレットペーパー、タオル、ウェットティッシュ、ハサミ、カッター、文房具、充電コード、紙コップ、割り箸などは、当日セットとして別にしておきます。
なお、段ボールには「当日使用」と目立つように記載しておきましょう。
引っ越し荷造り時の段ボールへの詰め方
段ボールに荷物を詰める際は、以下の3つのポイントに注意しましょう。
軽いものを上に、重いものを下に
段ボールに荷物を詰める際は、重いものを下に、軽いものを上に置くのが基本です。段ボールのバランスが安定し、運搬中の揺れによる破損リスクを軽減できます。
また、重いものを下にすると、箱を持ち上げる際の負担も軽くなって、引っ越し作業がスムーズになりますので、この順序を守って梱包してください。
さらに、梱包した段ボール自体も、重いものは下に、軽いものは上に、それぞれ積み上げます。そして、使っていない部屋やクローゼットなど、邪魔にならない場所に保管しておきましょう。
隙間を埋める
段ボール内の隙間は、新聞紙やプチプチを使って埋めることで、荷物を固定しましょう。段ボール内に隙間があると、運搬中に荷物が動いて破損する可能性があるからです。
新聞紙やプチプチを隙間に入れておけば、クッション材となって中身がぶつかり合うのを防いでくれます。どちらも不足気味の場合は、タオルや古い布も活用してください。
中身が分かるようラベリングする
段ボールには、中に何が入っているかを明記しておきましょう。あらかじめラベリングしておけば、新居で荷物をスムーズに運び込めます。
具体的には「食器類」「冬物衣類」「リビング用」など、段ボールごとに運搬先の部屋名や内容物を記載していきます。また、割れ物や液体類など、取り扱いに注意が必要な荷物には「取扱注意」や「上積み厳禁」といった表示を追加しましょう。
引っ越しで荷造りする時のコツ
ここからは、引っ越しで荷造りする際のコツについて、アイテムごとに解説します。
本
本を段ボールに詰める際は、凹みや破損を防ぐために丁寧に梱包しましょう。
本は「寝かせて積む」方法がおすすめです。大きな本を下に、小さな本を上に積み重ねると安定しやすくなります。
もし本を立てて収納する場合は、変形のリスクを避けるため、背表紙を下にするか、背表紙が地面と平行になるように配置しましょう。
また、段ボール内の隙間は緩衝材や新聞紙で埋めると、本が動かず安全です。特にアルバムや写真集などの貴重品は、プチプチで包んでください。
服
意外に知られていませんが、服は衣装ケースやタンスに入れたまま運んでもらうことが可能です。
運搬中にケースのフタが開かないよう、養生テープでしっかり固定し、割れ物や貴重品は必ず取り出しておきましょう。ただし、運べるのは重量制限以内の場合に限られるため、事前の確認が必要です。
掛けている洋服については、引っ越し業者が当日提供する「ハンガーボックス」を活用すると便利です。
ハンガーにかけたまま梱包し、新居ではそのままハンガーパイプにかけられます。服がシワになりにくく、荷解きの手間も大幅に省けます。
食器
食器は割れやすいため、丁寧に梱包しましょう。
平らなお皿は1枚ずつ新聞紙や緩衝材で包み、四隅を折り込んで最後にテープで固定します。平皿は上からの圧力に弱いため、段ボールには立てた状態で詰めるのがポイント。
一方で、深皿や丼、小鉢などの深さのある食器は横向きに詰めると安全です。どちらの場合も、段ボール内で動かないよう注意して梱包しましょう。
ガラス製や陶器の食器も、1つずつしっかりと梱包します。ワイングラスやマグカップなどは立てた状態で詰め、高さがそろうものを並べると安定します。段ボール内の隙間は、タオルや緩衝材で埋めることで輸送中の動きを防ぎ、破損リスクを軽減できますよ。
家電・家具
家電や家具は毛布や緩衝材で包み、運搬時のキズや衝撃を防ぎましょう。家電は配線をまとめ、コード類をビニール袋に入れてから本体にテープで固定すると、紛失や絡まりを防げます。
冷蔵庫や洗濯機は引っ越しの数日前に電源を切り、水抜きや霜取りを済ませてください。テレビやモニターなどの精密機器は、専用の梱包材や元の箱があればそちらを活用します。
家具は分解できるものは分解し、ネジや金具を小さな袋に入れて管理します。タンスや衣装ケースは中身を抜かず、扉や引き出しを養生テープで固定すれば、そのまま運んでくれますよ。
小物
アクセサリーなどの小物は、整理しながら梱包するのがコツです。カテゴリーごとに分け、ビニール袋や小さな箱にまとめてから段ボールに詰めると、荷解きがスムーズに進みます。
例えば、文房具やケーブル類は束ねて袋に入れ、「リビング用」「書斎用」などのラベルを貼っておくと便利です。
壊れやすい小物は、1つずつプチプチで包むか、小さなケースに入れて保護します。また、引き出し内の小物をそのまま運びたい場合は、ラップで包むのもおすすめです。
段ボールに詰める際は、空いたスペースに緩衝材を入れ、小物が動かないようにしてください。
液体類(調味料・洗剤など)
液体類を梱包する際は、漏れを防ぐことが最優先です。調味料や洗剤などのボトルは、フタをしっかり閉め、さらに養生テープで固定します。
漏れが心配なものは1つずつビニール袋に入れ、万が一漏れても他の荷物が濡れないようにしましょう。箱詰めする際は、同じ液体類をまとめ、段ボールの中で立てて配置するのが基本です。
割れやすいガラス瓶はプチプチや新聞紙で包み、段ボール内に隙間ができないよう緩衝材を詰めて固定します。
冷蔵保存が必要なものは、引っ越し当日にクーラーボックスを使うと安心です。新居で荷解きしやすいよう、段ボールには「液体類」や「ワレモノ」などと明記しておきましょう。
刃物
刃物は、厳重に梱包して安全性を確保しましょう。
包丁やハサミは、まず刃の部分を厚手の布や新聞紙で包み、養生テープでしっかり固定します。その上からプチプチを巻き付けると安全です。包丁は専用のカバーがあればそれを使い、ない場合は厚紙で自作しましょう。
刃物を段ボールに詰める際は、刃先が外に出ないよう注意し、他の荷物と分けて梱包することをおすすめします。さらに、段ボールには「刃物」と明記しておくと、引っ越し業者や自分が扱う際に安全です。
カッターやハサミなどは、まとめてビニール袋に入れて緩衝材で包んで紛失を防ぎましょう。
【重要】引っ越しで荷造りする際の3つのポイント
引っ越し荷造りを効率よく進めるために、以下の3つのポイントを押さえておきましょう。
1.新居に合わせて荷造りする
荷造りを進める際は、新居での収納スペースや間取りを意識しながら進めましょう。そうすることで、荷解き作業が格段にスムーズになります。
例えば、引っ越し先のクローゼットや収納棚に合わせて段ボールを分類する、新居の部屋ごとに「リビング用」「寝室用」などラベリングしておく、といった工夫を施せば、搬入もはかどります。
新しい生活を気持ちよくスタートするためにも、後先考えずに荷物を段ボールに詰め込むのではなく、新居に合わせて荷造りするようにしましょう。
2.貴重品は梱包しない
現金などの貴重品は、段ボールに梱包せず手荷物として持ち運びましょう。一般的に引っ越し業者は、貴重品が梱包された荷物を取り扱うことができないからです。
国土交通省は、引っ越し時のトラブルを未然に防ぐため「標準引越運送約款」というルールを定めており、特定の貴重品は取り扱えないことを明記しています。国内の引っ越し業者は、このルールに従って業務を行っているのです。
具体的には現金のほか、預金通帳、キャッシュカード、実印、有価証券、宝石類、貴金属などが「貴重品」に当たります。また、絵画や骨董品といった高価な美術品についても、引っ越し業者は運べません。
これらの貴重品は自分のバッグなどにまとめて、引っ越しが終わるまでは常に手元で管理しましょう。
3.不要なものは早めに処分する
引っ越し作業で不要なものが出てきた場合、特に粗大ゴミは早めに処分しましょう。処分しないままギリギリまで持っていると、引っ越しのタイミングで処分できず、一旦新居に運ぶ羽目になるからです。
ゴミの回収日は、自治体によって異なります。特に、粗大ゴミを処分できる日は限られますので、早めに出しておかないと引っ越し当日までに処分できない可能性があります。不要となった家具や電化製品などは、余裕を持って処分を進めていきましょう。
引っ越しは「不要なものの断捨離」ができる大きなチャンス。新居で使う予定がないものや、長期間使っていないアイテムはこの機会に手放すのがおすすめです。
引越し専用「新居の収納づくりプラン」
最後に、収納のプロが忙しいあなたに代わって引っ越しをお手伝いするサービスを紹介します。
おうちデトックスの引越し専用プラン
引っ越しはきれいなお家をつくる、絶好のチャンス。しかしこの記事で紹介した通り、荷造りや新居の収納準備に多大な時間がかかります。
そんな方におすすめするのが、プロの収納サービスへの依頼です。サービスを活用すれば、効率よくスムーズに新生活をスタートできます。
おすすめのサービスは、おうちデトックスの新居向けに特化した収納サポート「新居の収納づくりプラン」では、荷造り・荷解きをはじめ、家具の採寸、新居の収納グッズ準備など、引っ越しのタイミングで理想の環境づくりを、整理収納のプロがお手伝いします。
家族構成やライフスタイルに合わせて最適な収納方法を提案してくれるので、引っ越し後の片付けに悩む必要がありません。さらに、お引越し2ヶ月後のアフターフォローもあるので、実際に暮らしてみて収納の見直しもしてくれます。
忙しくて荷解きや整理に手が回らない方や、新居での暮らしをより快適にしたい方は、プロの手を借りて、快適で使いやすい住まいを実現してください!

詳しくはこちら! →【引越し専用】新居の収納づくりプラン
お客様の声①
はやくも引っ越しからひと月が経ちました。
おかげさまで混乱なく新しい生活がスタートでき、それが継続しております。
これもおうちデトックスの皆様のサポート力の高さのおかげです。
あらためてお礼を申し上げます。ありがとうございます。
お客様の声②
夫より送信いたしました熱のこもった感謝のメールのとおり、プランニングからご提案、梱包、開梱に至るまでの手熱いサポートに大変満足し、感謝しています。
特に、旧居より狭い物件への転居での困りごとでありました、動線を考えたうえでの大型家具の配置、収納はすばらしく、依頼させていただいてよかったと、夫婦で話しております。
まとめ
今回は、引っ越し荷造りをスムーズに進めるために準備するものやスケジュール、荷物ごとのコツや荷造りのポイントについて解説しました。
新居での暮らしを快適に始めるには、計画的に引っ越し準備を進める必要があります。一方でやるべきことがあり過ぎて、準備の時間を確保できない方も多いはず。
そんな時は、プロの収納サービスを活用することも一つの手です。おうちデトックスの引っ越し専用「新居の収納づくりプラン」は、新居の収納づくりに特化したサービスです。
この記事を参考に、楽しく充実した新生活をスタートさせてくださいね!